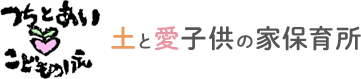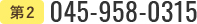ブログ
- TOP
- ブログ
安心安全と伝えていく事
あっ・・・もう年末だ・・・夏が暑すぎたせいか、年末の実感もないまま、暦だからクリスマス会の準備や年賀状のことやらが進んでいます。自分の子どもの学童の迎えに行ったときに「息が白いね~」という言葉で、冬になったんだなぁ~という思いになることができました。先日、もちつきのはなしになりました。餅つきはするけど、餅は子どもたちそれぞれが鏡餅を作るためで食べさせることはしないで持ち帰ってもらう。食中毒のリスクも高いし、詰まらせたら大変!っと言っていました。そうなんだぁ~うちは食べさせてますよ。と言うととてもびっくりしていました。そんなリスクの高い事してんの!事故があったらどうするの?こちらもびっくりで、何のための餅つきなの?鏡餅を作るためだけのもちつき?子どもはお餅つき=鏡餅づくりにならないのかなぁ~食べるお餅は買って食べるもの。食べ物は自分でつくらないで買うものってなってしまわないのかなぁ・・・自分たちで作ったものは衛生的じゃないから買って食べたほうが安全。確かにそうだとは思うのです。食べ物を作ることを仕事として行うのだから、そこでのミスはしてはいけないから衛生的にしていくのは当たり前だと思います。(会社を経営していくという立場として)安全安心があるのは大前提ですが、安心安全を求めるあまり「生活していく」ことがおろそかになっているように思ったりもします。保育園という立ち位置だからそこを維持していくのは当たり前と言われるのは、もっともです。そこをおろそかにすることはしたくないのですが、それが過剰になってしまうことで、今ままで培ってきた文化を壊していく事に繋がってはいないだろうか?と思うのです。保育園って日中保育ができない家庭のために子どもたちと大人が生活をしていく福祉施設です。安心安全を大前提としながらも、文化の継承を身をもって経験することで日本のことを学んでいき、受け継いでいくという視点も含まれていると思っています。だからこそご飯も和食中心であったり、さまざまな行事や遊びを行っていると思います。お餅つきでは参加した家族とお餅をついて、その時にみんなで食べます。子どもたちと味噌を作って、それで味噌汁を作ります。魚をさばいて干物を作り、ご飯のおかずになります。お当番の年長児はご飯を研いでくれます。どんど焼きをしてそこではお団子も食べます。いままで何もなかったから、これからも何も起こらないとは思っていません。気を付けても起こる時には起こってしまいます、だからこそ気を付け続けないといけないです。食育というきれいな言葉ではなく、生きるために必要なこと自分で食べるものは自分で作れるように自分の目の前にあるご飯はいろんな人の手がかかり、思いがのって目の前にあるんだよ。それを実感してもらうには、身をもって経験することが必要ではないかと思うのです。「食べることは生きること」生きていくということを考える。お金を払えば何でも食べられるけれど、それだけでいいのかな?自分のために作る、作ってもらうという思いを感じられること。それはお金ではなかなか買えないんじゃないかなぁ・・・安心安全を求めすぎることで、子どもたちはどう育っていくのだろうか?子どもたちに何を残していけるのだろうか・・・
たもつ(第2)
夏の思い出
今月の園だよりは「夏の冒険」というテーマで職員のみんながそれぞれの冒険や思い出を書いてくれました。私もそのお題に沿って書きました・・・学生の頃にした「北海道一周旅行」についてです。お金に余裕がなかった学生時代だったのですが、夏休みに2週間くらいかけて友人と二人でバイクで北海道1周しようぜ!となり、若いからできる勢いに任せてすることになりました。
ナビをバイクにつけることなんてない時代なので、頼るのは道路の標識と地図(スマホもないので紙の地図)テントに寝袋にガスコンロに・・・毎日野宿覚悟で始めた旅行でしたが・・・ひたすらテントは耐えられない・・・(夏でも結構寒かった・・・)3日に1回は布団で寝たい・・・となり、安いライダースハウスを探したり(アウトドア派ではないので・・・)スーパー銭湯に行ったら、なけなしの財布を盗まれて警察に行ったり・・・(お金はすられて財布はゴミ箱に・・・おかげで免許証は無事)
そんなこともありましたが、いろんなところに行きました!出会いがありました!納沙布岬や知床、網走や摩周湖、襟裳岬・・・そして、本州にはないであろうひたすらまっすぐの道!(しかも車もほぼいない!!)
それもこれもひっくるめてあの時にしかできないことだったなぁ~と思っています。なぜって、一気に1周できる時間があったから!(働いていたり、家族がいたら、なかなか無理なこと・・・)そう考えると、若い時の経験ってとても貴重なんだなぁ~と思います。
若い時の経験、若さゆえの勢いってとてもすごい事なんだと40歳後半の自分は思っています。若さゆえの経験・知識不足はしょうがない事。頭ではわかっているつもりだけど、エネルギーが勝ってしまう。それが良い結果だったり、悪かったり・・・人としてのラインをこえなければ、それはこれから歩んでいく糧になるんだと思っています。そう思うので、子どもたちには自分で考え、判断して、エネルギーをぶつけてほしい!成功することより、失敗したほうが記憶に残ると思ています。嫌な記憶を消すために、次は成功しようと考えると思うのです。
泣いて、笑って、考えて・・・自分の経験値を上げていってほしいと思っています。
失敗したってしょうがない!次行こう!!と認めてくれる社会の目がもっともっと多くなりますように
第2 たもつ
幼保小交流で思うこと
この頃、雨が多くてじめじめとしていますね・・・去年はいつ梅雨?と思っていたほどなので、梅雨時期らしいと言ったらそうなのでしょうが、私が小さい時に比べると局所的な大雨が多くて被害が大きい・・・全国まんべんなくしとしとと降ってもらえればうれしいですが・・・
そんな蒸し暑い時期ですが、先日、幼保小の交流が近くの小学校であり、5歳児いるか組が行ったのについていかせてもらいました。歩いて15分くらいですが、行きも帰りもみんなもりもりと歩いてあしか組の時とは違う、やっぱりいるか組になると心持ちが違うのかと感心!
交流ではどんなことをしたかというと、体育館で5年生とのレクリエーション、1年生の教室で1年生とカプラでの遊び。他にも保育園がきていたので、それぞれ交流ができるようにチームとなって行いました。
1年生とのカプラ交流は初対面なところもあり、みんなでなんか作ろうよ!!とは子どもたちの力だけではできずに大人の手も借りながら作っていた感は否めませんでした・・・(けど、それはしょうがないこと。そこから、これからの交流をどうするかのきっかけづくりになれば良いかとは思います。)そして、5年生の子たちの園の子たちへの気遣いがとっても素敵!!5歳くらいしか離れていないのにこんなにも違うのか・・・大人になってからの5年とは比べもにならん・・・恐るべし子どもの成長・・・と再認識(笑)
そんな再認識を楽しみつつカプラ交流の場で見学をしているときに小学校の先生と話をした際・・・
保育園で最年長の子どもたちが小学校に行くと最年少になり、いままで保育園でできていたことを上の学年の子がしてくれているという現実もあるからどこまで手をかけてあげるのが良いのでしょうね~?
とぼそり・・・なので・・・保育園では何でもできるけど、環境が変わることで不安も大きくなるだろうし、園の中では頑張っているかもしれない。そこを上の学年の子どもたちが甘やかしてくれるのはあってもよいんじゃないですか?と伝えました。
できることがあれば、自分から離れていくし、そうでなければ甘えるだろうし、まずはお兄さんお姉さんって優しいんだなぁ~そんな人になりたいなぁ~っという憧れが持てる環境がとても大切なんだろうなと思っています。
それは保育園でも一緒で年長児がいろんなことができるのも先輩たちを見てきたからあんないるかになりたい!いるかになったからあれもこれもやりたい!その思いはとっても大切!
それは保育園でも小学校でも中学校でも高校でも大人でも一緒なんじゃないかなぁ~憧れるって生きていこうとする力の源なんじゃないかなぁ~だからこそ幼保小の交流で憧れるお兄さんお姉さんにあえて、あんなふうになりたいなぁ~と思えるきっかけづくりになってくれれば嬉しいなと思うのでした。
第2 たもつ
もう6月に・・・
新年度が始まり、更新できたのは調理補助募集のお知らせのみ・・・細々とできればよいかと思ってはいたのですが、それにしても細々というより先細り・・・もしかして、このブログを見てくれていた人がいるかもしれないのに・・・そして、新年度開けた時くらいはしっかり書かないと、と思いつつこの時期にまで来てしまいました・・・
今日は健康診断でした。
園医の榊原先生がきてくれ、子どもたちの健康状態を見てくれます。もう園医になっていただき、20年近くになります。私が園長になってから、先生を送迎することがあるのですが、その車の中で話したことから思ったことを書ければなぁ~なんて思っています。
第2の診察が終わり、本園に向かう途中、「見えること」と「聞こえる」についての話になりました。
健常(この言葉が適切かわかりませんが、便宜上使わせてもらいます)の人にとっては見える情報はとても大切というけれど実は聞くことの情報というのは想像以上にあるという事なのです。
その話の中で出してくれたのが、ヘレンケラー。ある時、取材をしていた記者がヘレンケラーにインタビューをした時、
(見えない)目と(聞こえない)耳のどちらかが直るとしたらどちらが良いですか?
という質問をしたとのこと(意地悪な質問・・・)。その質問に対して、ヘレンケラーは聞こえる耳が欲しいと答えたの事です。
えっ・・・聞こえることを取るんだ!見えることのほうが、情報取得のためには良いんじゃない?と内心思ってしまいました。
しかし、あとから説明を聞くと確かに・・・と納得。見えなくても、触ったり、他の人からの声で自分の周りの状況やその名前や性質は知ることができます。しかし、聞こえないと物体としては見えるけど、言語での認識ができないということは目の前にあるものの名前もわかることが難しいという事。
私は目も見えて、耳も聞こえます。
生まれついて見えないこと、聞こえないことが不自由だろうな、だからこそ何か役に立てることはないだろうかと考えています。しかし、その状態が本人の中では普通なので、必要以上の手出しはおせっかいの何物でもないんだろうなぁ~とも思ってしまいます。
自分ができることができない人はかわいそうなのか?ハンデがあって、かわいそうだから手を貸すのか?そうじゃないんだろうなぁ~
おたがいさま
なんだろうなぁ~みんないろいろあるんだからお互いさまなんだろうになぁ~どんな人でも同じ社会で暮らしていける世の中になってほしいなぁ~と思うのでした。
(第2)たもつ
5歳児交流
寒い、寒い・・・早く春が来ないかなぁ~というよりは、なんかいつ冬本番が来るのか?と待っていたら、あれ?春になるの?
という感じが否めない今日この頃・・・もすっかり梅の花はきれいに咲いて、またこの時期が来たなぁ~と思います。
そんな時期に近くの保育園4園が集まって、交流をすることになりました。今回集まったのは2回目?3回目?くらいでまだまだ他の園の子の名前までは・・・
それぞれの保育園の紹介をしてから、じゃんけん列車をして、次に4月から行く学校ごとに分かれてのクイズ大会をすることになりました。
1つの小学校でそれなりの人数になるところやいくつかの小学校が集まって1つのグループになるところ5つくらいのグループに分かれてのクイズ大会でした。
色々な保育園でのグループだけど、その先の小学校では一緒のクラスになるかもしれない!そんな気持ちがあると、気持ちはぐぐっーと近くなるだろうな~だからなのか、クイズの問題をだすと話し込んでいる姿が見られました。最初はよそよそしいけど、ちょっとずつ話せるように・・・
今までの積み重ねももちろんあるけれど、目的地(就学先)が一緒の子がいる安心感はあるだろうなぁ~
うちの保育園は60人定員です。これは0歳児から5歳児まで。そのなかで5歳児は12人。12人がみんな同じ学校に行くことはないので、1人だけということもあります。もうこの時期、子どもたちは自分がどこの学校に行くのかも知っていますし、同じ保育園の仲間が自分とは違う学校に行くのもわかっています。その中で、小学校という楽しみだけど未知数なところに行く顔をこの時期に知ることができるのは心強いだろうなぁ~と思います。
クイズの後には自由時間でしたが、同じ保育園で固まってというよりは、グループごとに遊んでいた感じがあります。
保育園で過ごしている時間は長い子で6年。その中で毎日の生活を共にする仲間の絆は強いと思います。強ければ強いほど、外に羽ばたいていくときに不安は大きいでしょう。けれど、これから羽ばたいていくみんなに、大丈夫だよと伝えてあげたい。
だって、保育園で仲間ができたじゃん!
だから、これから進むべきところでもきっと仲間はできるよ。恥ずかしいかもしれない、不安かもしれない・・・色々な思いはあるけれど
きっと相手もドキドキしているはず
ちょっとずつで構わないから友だちを、仲間を作ってほしいと思います。保育園の時よりもっと仲良くなれる友だちができるかもしれない!
世界はとっても広いから人は人とかかわることで人になるので
だからこれからも色々なことに触れあって、たくさんのことを思って考えてほしいと思うのでした。
第2 たもつ
お問い合わせ
ご相談、ご見学についてなど、お気軽にご連絡ください。
-
本園045-953-2779045-953-2779
-
第2045-958-0315045-958-0315
【受付時間】9:00~17:00(平日のみ)